 |
 |
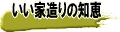 |
|
|
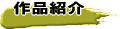 |
|
|
 |
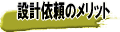 |
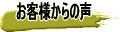 |
 |
 |
|
|
������HP��
�@�@�@���T�X�V�I |
|
|
�ꋉ���z�m������
�L�����
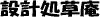
|
��530-0035
���{���s�k�擯�S
�P����7-13-303
TEL:06-4800-2711
FAX:06-4800-2712 |
|
| �������N�p�o�i�[ |
 |
|
|
|
|
|
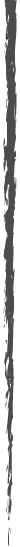 |
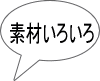 |
 |
�N���b�N����ƁA�o�b�N�i���o�[
�������ɂȂ�܂��B��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���v
�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@�@�u�Y�Q�v |
|
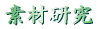 �@ �@
|
�@�ߔN�Y�̌��p����������A�Y�Ɋւ��鏤�i�����ɑ�����������Ă��܂��B���ɂ͂��̏��i�邽�ߓs���̂����悤�Ɋg����߂����L���������܂��B�����ŁA�Y�̊�b�I�Ȃ��b�����Ă݂����Ǝv���܂��B
���Y�̍\����
�@�Y�́A�c���ɒʂ���ׂ��p�C�v�𑩂˂��g�D�E�\���ɂȂ��Ă��āA���ׂ̍��p�C�v�̓����ʐς��P���i���w�̓��ʂ̑傫���j�Ŗ�300�u�i90�E180���j������܂��B���̑��E�������Y�̍ő�̓����ł��B
���Y�̎�ށ�
�@�Y�͏Ă����x�ɂ���đ傫�����Y�ƍ��Y�ɕ������܂��B���Y�Ƃ�700�`1000���̍����ŏĂ��A�^���ԂȂ܂܊������o���Ĕ��D�������āA�_�f���R�ɒ������Ă����܂��B�Y�����ł��ĉΎ������ǂ����߁A�g�[�p�E�����p�Ƃ��čœK�ł��B���APH8�`9�̃A���J�����ŕ\�ʂ��Ƃ��Ȃ��̂ŏp�Ƃ��Ă��K���Ă��܂��B��ʂɗǂ��m���Ă���a�̎R�̔����Y�Ȃǂ�����ɂ�����܂��B
�@����ɑ��A���Y�Ƃ�400�`700���ʂ̒Ⴂ���x�ŏĂ��A���̒��ɓ��ꂽ�܂��R�����Ă����܂��B�ގ��͎���ɂ����܂����A��ʂɏ_�炩�������\�ʐς͔��Y���L�����߁A�����ށE�����ȂǂɌ��ʓI�ł��B���A�Εt�����ǂ��ׁA�����Y�Ȃǂɂ��g���Ă��܂��B
�@���ɁA�Y�̓����ɂ��Ă��b���܂��傤�B
�@�傽������Ƃ��ẮA��������p�@�����L��p�@���E��p�@���Ȃǂ��������܂��B
<�����ނƂ��Ă̒Y>
�@�Y�ɂ́A��q�������E���Ƒa�����i�����͂��������j������A����ɂ���đ����̐����C���キ�z�����܂��B�キ�z�����邱�Ƃɂ�莼�x��������Ƌz�������C����o���܂��B
�@���A�����ނɋ��߂���͎̂��C���z������f�����肷�鑬���ł��B���ɑ����̎��C���z���ޗ��ł����Ă��A���x���x��������f���o���Ȃ���ΈӖ�������܂���B
�@�����̒������ʂ̎����ɂ��ƁA�h���V�[�g�̋��ł͔N�ɉ��x��100�����z�����I���Ă��邱�Ƃ��m�F����܂����B����ɑ������Y�̋��͔N�Ԃ�ʂ�95���ȉ��ɗ��܂�A���I�͔F�߂��Ȃ��ƕ���Ă��܂��B
�@���̂��Ƃɂ�茋�I�˃J�r�˃_�j���͌��I�ˍޖ̕��s�˔��A���ɂƂ��ėL���Ȓ����ނƌĂׂ�̂ł��B
�@����ł́A�ǂ�ȒY��I�ׂΗǂ��̂ł��傤���B�܂��A���E���̑傫�����Y���g���Ă�����́B����́A���Y���������ł��̂ŃR�X�g�̓_������L���ł��B
�@���A�{�H���E��U�̎����l����ƕs�D�z�ŕ�܂ꂽ���̂��g���������ǂ��ł��傤�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Y�Q�@�ւÂ�
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| �C���X�g�F�@�g����q |
|
|