 |
 |
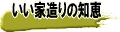 |
|
|
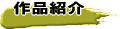 |
|
|
 |
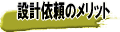 |
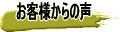 |
 |
 |
|
|
|
|
|
一級建築士事務所
有限会社
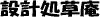
|
〒530-0035
大阪府大阪市北区同心
1丁目7-13-303
TEL:06-4800-2711
FAX:06-4800-2712 |
|
| ↓リンク用バナー |
 |
|
|
|
|
|
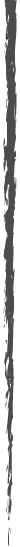 |
|
|
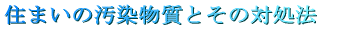
シックハウス症候群などへの対処法
|
|
|
私達が、普段何気なく過ごしている住宅には、目に見えない様々な毒性物質が潜んでいます。
特に新素材を使用したマンションや一戸建て住宅の新築時には、多量の有害物質があふれ、空気を汚染し人体に悪影響を及ぼすことは、シックハウス症候群などとして近年の研究で明らかにされています。
そこで今回は、私達の健康を脅かす汚染物質とその対処法について述べていきたいと思います。
<汚染物質の種類と性質>
住宅に使われている建築材料の中には、空気環境に影響を与えるものがあります。室内の空気が汚染されると、人の呼吸器系、血液と循環器系などに重大な影響を与えます。
人は一日に約四畳の部屋の容量に相当する程の空気を摂取すると言われており、無意識のうちに、空気中の汚染物質を体内に取り入れているのです。
空気中の汚染物質は大まかに四つに分類され、まず一つめはホルムアルデヒド、有機化合物、窒素、硫黄オゾン等の化学物質。二つめが、ガラス繊維、アスベスト、重金属等の無機粒子・繊維状物質。三つめが花粉、カビ、粉塵等の有機粒子状物質。そして、バクテリア、細菌、ウイルス、ダニ等の微生物・細菌類。
これらの汚染物質の中でも、建築材料に含まれる化学物質の影響が、明らかになりつつあり、多くの人々を不安にさせているのです。
現代社会では、化学物質と全く関わりを持たないで生活するのは、大変なことですが、化学物質の特性を知らずに用いていると、気付かない間に人体にダメージを受けていたということがある為、それぞれの性質と対処法を知っておく必要があるかと思います。
建材に含まれる化学物質の中でも最も人体に影響の大きい有害物質はホルムアルデヒド、揮発性有機化合物(VOC)、農薬等の防腐・防虫剤の三種類です。
ホルムアルデヒドは、刺激臭のある無色の気体で、空気中の濃度が0.1ppm程度から刺激臭が、0.5ppm程度から目に刺激を感じるようになる。急性毒性が強く、突然変異性もあり厚生省が劇物に指定しており、慢性作用として肺活量の減少や、咳を伴う気管支炎や喘息のような症状があり、発ガン性物質にもなるとされています。ホルムアルデヒドが多く含まれる接着剤は含有量の多い順から、ユリア樹脂系、メラニン樹脂系、フェノール樹脂系です。
これらは、主に木材の接着剤として、合板や集成材に使用されています。合板からのホルムアルデヒドの放出量は、日本農林規格(JAS)で、F1・F2・F3という三つのレベルに分類されています。F1が、最も放出量が少なく、規格外でF0というホルムアルデヒドが出ないものもあります。
揮発性有機化合物(VOC)は、数百種あるといわれ、それらには脂肪族・芳香族の炭化水素、塩素化炭化水素、各種ケトン類、アルデヒド類等が含まれます。性質、毒性共に様々ですが、共通する性質としては常温では液体で、揮発しやすく空気と一緒に肺に入り血中に移動します。
脂肪溶解性があり、皮膚や目からも吸収され、引火性の強いもの等もあります。
中毒症状として、軽度の場合では精神興奮、倦怠感、頭痛、目眩、吐き気等があり、中度では吐き気、食欲減退、息切れ、動悸、手足のしびれ等が、重度の場合は小脳麻痺によって死亡することもあるのです。
有害な有機化合物は、ペンキ、水性二ス、ラッカーの溶剤、床ワックス、畳の防水加工剤・防蟻剤、壁紙類の難燃加工剤・接着剤溶剤等の建材に含まれています。
農薬を主とした防腐・防虫剤・シロアリ駆除剤は、建材としては畳や土台、床下の土壌に使われています。
現在一般に流通している畳には、ダニの発生を防ぐ為に有機リン系殺虫剤を染み込ませた防虫加工紙が、縫い込まれており、この薬剤の量は水田の二十から三十倍にも昇ります。
ちなみに、多くの公共住宅の工事仕様書には、畳の中に防虫加工紙を使用することが定められています。
畳以外では、土台などの木材防蟻剤と床下へのシロアリ駆除剤等が使用されており、現在住宅で発生している中毒事故は、床下のシロアリ駆除剤によるものが多いようです。
シロアリ駆除剤は、木材に塗布、加圧注入される他、床下土壌に注入されることもあります。
住宅金融公庫仕様書でも、シロアリ駆除や防腐処理剤の使用を義務付けていましたが、1994年に「ヒバやヒノキのような耐腐朽性や耐蟻性の大きい木材を使用すれば、薬剤処理は必要ない」と改められました。
その他にも、家庭用の殺虫剤、防虫剤やトイレの芳香剤による室内空気汚染も指摘されており、見直す必要があるようです。
<対処方法>
それぞれの汚染物質に対して対処方法は異なりますが、基本的には室内の空気汚染を引き起こす物質を避けることです。
これから新築をするのであれば、使用する建材をあらかじめ選択出来ますが、もうすでに化学物質過敏症やアレルギー等に悩まされている人であれば、限られた中での対策法を考えなければならないと思います。
床下のシロアリ対策としては、忌避効果のある木酢液やヒノキチオールを使用したり、床下の湿気をコントロールする為に木炭を敷いたり、床下換気扇を取り付ける等が上げられます。但しすでにシロアリ駆除剤が床下にまかれているのであれば、床下の有害な薬剤が外に吐き出されて近隣への被害が考えられるので、床下換気扇の使用は避けるべきです。
身近なものでは、トイレ等の防臭剤や殺虫剤、蚊取り線香、衣類の防虫剤を使わないようにする等の方法がありますが、換気をこまめに行ったり、部屋を密閉し暖房器具を用いて有害物質を揮発させた後、窓を開け放って揮発した有害物質を一気に外部へ出てしまう「ベイクアウト」を行ったり等の方法もあります。
又、カーテン等に、有害物質を付着させる加工を施すことも出来るようになってきました。(光触媒加工など)
畳に関する対策としては、国産の素材で、無農薬・有機栽培されたわら床とい草の畳表のものに変えるということが考えられます。又、畳に発生するダニ・カビ対策として、調湿作用のある炭入り畳やセラミックで抗菌・防ダニ加工した畳表を使用するという方法もあります。
予算があるのであれば、床材を天然木、コルク、天然リノリウム等に変えたり、壁材の下地をプラスターボードやF1合板に張り替えてから仕上げ材を、紙や布クロス、天然木、塗り壁に変えると効果的です。
天然素材の中でも、アレルギーの原因となるものもあるので、使用前に手にとって、臭いを嗅いでみたりすることをお薦めします。
身近な努力と工夫で、ささやかな健康的空間を手に入れることも可能かと思います。
不安がらずに正しい知識をもって心安らかに暮らすことこそ、健康的生活といえるのではないでしょうか?
|
|
|
by 中原 賢二 |
|
|
| イラスト: 吉川佳子 |
|
|
|
designed by 設計処草庵/大阪市北区同心1丁目7-13-303 TEL:06-4800-2711
|
|
|
|
|
|
|